熊谷知事の千葉県は、地方自治体においては越権行為と捉えられる可能性がある夫婦別姓制度の検討に関し、回答者の7割近くが50歳以上となった大幅に偏った状況であるが、選択的夫婦別姓制度を導入した方がよいとの者が36.9%であったことを発表した。
千葉県では、県民を対象とした意識調査となる。令和6年度「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査」を実施した。この調査は、県における男女共同参画の意識の変化や実態を把握し、今後の県の施策を推進するための基礎資料とすることを目的とするとともに、社会情勢の変化を踏まえ、選択的夫婦別姓制度や男性の育児休業取得の推進などの調査項目を新設している。
調査対象は千葉県在住の満18歳以上の個人、標本数は2,000人、標本抽出法は住民基本台帳に基づく層化二段無作為抽出、調査方法は郵送により調査票・返信用封筒を配布し郵送・オンラインで回収、調査期間は令和6年10月15日から11月5日、回収結果は636(31.8%)となった。
アンケートの回答者の属性は、性別は、女性が52.8%、男性が42.6%となった。年齢は、70歳以上が29.1%、60~69歳が18.2%、50~59歳が19.3%、40~49歳が14.3%、30~39歳が9.3%、20~29歳が6.8%、18~19歳が0.9%となった。
新設された『選択的夫婦別姓制度についての考え』の質問は、「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方がよい」が12.9%、「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい」が37.3%、「選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい」が36.9%で、「無回答」が12.9%となっていた。
なお、日本の総務省によると、国と地方の役割分担に関しては、【地方公共団体は、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされ、地域における事務及び法令で定められたその他の事務を処理する】と定義している。また、国が本来果たすべき役割として【国際社会における国家としての存立にかかわる事務】【全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施】としている。
また、神奈川県の黒岩知事などは、選択的夫婦別姓制度・夫婦同姓制度などは地方自治体ではなく国が策定し検討するものであるとの旨の見解を示しており、特段の意見は示していない。
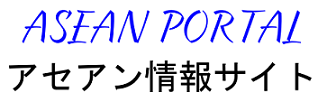

 アセアン10カ国情報
アセアン10カ国情報
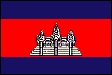

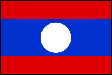
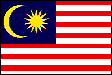
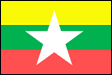
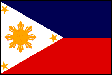
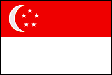
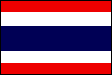
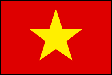

 環境省はフィリピンと気候変動緩和の協力意向表明書を締結
環境省はフィリピンと気候変動緩和の協力意向表明書を締結 福岡で外国人留学生就職フェア、いすゞ自動車・イオン九州等が参加
福岡で外国人留学生就職フェア、いすゞ自動車・イオン九州等が参加 高市政権はアフリカ・ブルキナファソの農業生産の向上支援、14億円の無償資金協力
高市政権はアフリカ・ブルキナファソの農業生産の向上支援、14億円の無償資金協力 総務省はカンボジア・ラオス・マレーシア等にデジタルインフラ等を講演
総務省はカンボジア・ラオス・マレーシア等にデジタルインフラ等を講演 齋藤知事の兵庫県は外国人が安心し就職し定着できるようグローバル人材活躍企業の認定へ
齋藤知事の兵庫県は外国人が安心し就職し定着できるようグローバル人材活躍企業の認定へ 茂木外相はフィリピンの深刻な交通渋滞緩和を支援、216億円の円借款
茂木外相はフィリピンの深刻な交通渋滞緩和を支援、216億円の円借款 山本知事の群馬県は外国人活躍推進業務の職員を募集、外国籍の者も応募可能
山本知事の群馬県は外国人活躍推進業務の職員を募集、外国籍の者も応募可能 フィリピン大統領が三菱商事の社長と会談、提案された投資を評価
フィリピン大統領が三菱商事の社長と会談、提案された投資を評価 高市政権は訪日外国人患者の受入強化へ、最大500万円補助金交付
高市政権は訪日外国人患者の受入強化へ、最大500万円補助金交付 松本大臣の文科省は経験を学び合うため韓国・中国・タイ・インドと教職員交流、約7,000万円投入
松本大臣の文科省は経験を学び合うため韓国・中国・タイ・インドと教職員交流、約7,000万円投入 3Dインベストメント、東邦ホールディングスによる買収防衛策に基づく情報提供要請へ回答書を提出、及び「不公正なプロセス」に対する懸念を表明
3Dインベストメント、東邦ホールディングスによる買収防衛策に基づく情報提供要請へ回答書を提出、及び「不公正なプロセス」に対する懸念を表明 フライトセーフティ・インターナショナル、シンガポールでGulfstream G700フル フライト シミュレータのFAA承認を取得
フライトセーフティ・インターナショナル、シンガポールでGulfstream G700フル フライト シミュレータのFAA承認を取得 アジア太平洋企業、Oracle Cloudの近代化を加速
アジア太平洋企業、Oracle Cloudの近代化を加速 タイ伝統 音楽・舞踊の夕べ
タイ伝統 音楽・舞踊の夕べ …and Action! Asia#04 -映画・映像専攻学生交流プログラム-公開上映・プレゼンテーション
…and Action! Asia#04 -映画・映像専攻学生交流プログラム-公開上映・プレゼンテーション FUN!FUN!ASIAN CINEMA 第1弾シンガポール映画『881 歌え!パパイヤ』上映
FUN!FUN!ASIAN CINEMA 第1弾シンガポール映画『881 歌え!パパイヤ』上映 映画で読み解くサンシャワー展!「ワーキングタイトル」国立新美術館で開催
映画で読み解くサンシャワー展!「ワーキングタイトル」国立新美術館で開催 東南アジアの短編ドキュメンタリー上映会Visual Documentary Project 2016
東南アジアの短編ドキュメンタリー上映会Visual Documentary Project 2016 淡路梅薫堂 江井工場
淡路梅薫堂 江井工場 インドネシア料理スラバヤ 調布店
インドネシア料理スラバヤ 調布店