-
 高市政権はウクライナの医療体制強化と公正報道の確保等を支援、62億円無償資金協力
高市政権はウクライナの医療体制強化と公正報道の確保等を支援、62億円無償資金協力
-
 福岡県はグローバル人材育成プログラム成果報告会、ベトナム現地で研修
福岡県はグローバル人材育成プログラム成果報告会、ベトナム現地で研修
-
 高市政権はケニアの衛生改善を支援、USAIDからの支援減少UNICEFに6億円無償資金協力
高市政権はケニアの衛生改善を支援、USAIDからの支援減少UNICEFに6億円無償資金協力
-
 フィリピン・アメリカと共同訓練、海上自衛隊のP-3C等が参加
フィリピン・アメリカと共同訓練、海上自衛隊のP-3C等が参加
-
 アルゼンチン産牛肉の輸入解禁へ、鈴木農水相は国産への影響は現時点では不明と
アルゼンチン産牛肉の輸入解禁へ、鈴木農水相は国産への影響は現時点では不明と
-
 茂木外相は避難民受入のエジプト支援で約5億円無償資金協力、大きな外交的意義があると
茂木外相は避難民受入のエジプト支援で約5億円無償資金協力、大きな外交的意義があると
-
 マレーシアで天皇誕生日祝賀レセプション開催、民生用原子力・AIの連携強化等
マレーシアで天皇誕生日祝賀レセプション開催、民生用原子力・AIの連携強化等
-
 高市政権はマーシャル諸島の食料生産増加を支援、国際移住機関に2億円無償資金協力
高市政権はマーシャル諸島の食料生産増加を支援、国際移住機関に2億円無償資金協力
-
 国際海事機関の事務局長がフィリピン訪問、日本郵船の研修所・商船大学を訪問
国際海事機関の事務局長がフィリピン訪問、日本郵船の研修所・商船大学を訪問
-
 インドのヨギ首相は日本を日の出ずる国と、山梨県は実質的な交流を先導すると
インドのヨギ首相は日本を日の出ずる国と、山梨県は実質的な交流を先導すると
- 最新ニュース一覧を見る
世界の都市総合力ランキング(Global Power City Index 2017) 東京は3位を維持、さらにスコアを伸ばし2位のニューヨークに迫る
弱みを改善し「交通・アクセス」「文化・交流」のスコアが伸長
東京--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- 一般財団法人森記念財団 都市戦略研究所(所長:竹中平蔵)が、2008年より調査・発表している「世界の都市総合力ランキング(Global Power City Index, GPCI)」の2017年の結果がまとまりました。GPCIは、世界の主要44都市を対象に、都市の力を表す様々な分野を総合的に評価した日本初のランキングであり、今年で10回目を迎えました。この10年間のスコアの変遷から、“東京の課題と可能性”が見えてきましたので、報告いたします。


東京は3位を維持、スコアを伸ばし2位のニューヨークに迫る
昨年初めてトップ3に入った東京は、上位2都市であるロンドン、ニューヨークと比べてやや弱かった「交通・アクセス」や「文化・交流」の分野での評価を高め、2位のニューヨークとのスコア差を縮めた。「文化・交流」では「海外からの訪問者数」、「交通・アクセス」では「国際線直行便就航都市数」が東京の総合スコアを高めた主たる要因である。
ロンドンは高い総合力で、他都市を大きく引き離す
6年連続で1位を維持したロンドンは、昨年からさらにスコアを伸ばし、他都市を大きく引き離した。「文化・交流」は昨年同様高く評価されており、「食事の魅力」や「海外からの訪問者数」などのスコアが伸び続けている。英国のEU離脱が今度首都ロンドンにどのような影響を及ぼすかは未知数ではあるが、人口が増加し、大規模都市開発が続いているロンドンの総合力は、当面の間は伸び続けると予想される。
経年分析で明らかになった“東京の可能性”
2007-2008年の世界金融危機以降、数年間にわたって都市力を落としていたロンドンは、2012年の五輪を機に都市力を回復軌道へと乗せることに成功し、さらに五輪以降も着実にスコアを伸ばし続けている。2020年に五輪を控えている東京は、ロンドンと同じ成長カーブを描くことができれば、近い将来にニューヨークを抜いて2位に躍り出る可能性も見えてきた。
世界一の都市を目指す東京の課題
トップ2都市との比較から見える東京の課題
東京は、1位のロンドン、2位のニューヨークと比較すると、「文化・交流」分野のスコアに大きな差がある。具体的には、ハイクラスホテル客室数などの「受入環境」や、文化・歴史・伝統への接触機会などの「文化資源」で大きく引き離されている。また、経済分野の「市場の魅力」や交通・アクセス分野の「国際交通ネットワーク」もこれら2都市の水準には達していない。東京がさらに総合力を高めて世界一の都市になるためには、「経済」および「交通・アクセス」分野における弱みを克服しつつ、「文化・交流」分野のスコアを大幅に高めていく必要がある。
分野別ランキングから見える東京の課題
昨年の分野別ランキングと比較すると、東京は「文化・交流」が5位から4位へ、「交通・アクセス」は11位から6位へと順位を上げた。その理由として、「文化・交流」は、「海外からの訪問者数」や美術館・博物館などの「集客施設」の増加があげられる。また、「交通・アクセス」では、昨年まで「国際線旅客数」としていた指標を「国内・国際線旅客数」へ変更したことによるスコア増や、「国際線直行便就航都市数」や「通勤・通学の利便性」においてスコアをあげたことなどが主な要因である。一方、「経済」は1位から4位へ、「居住」は6位から14位へ順位を下げた。「経済」は上位都市と比べてGDP成長率が低いことや、為替変動(円安)が影響したこと、「居住」では新たに追加した「社会の自由度・公正さ・平等さ」、「メンタルヘルス水準」の指標で評価を伸ばせなかったことが理由である。
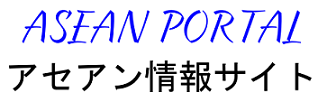

 アセアン10カ国情報
アセアン10カ国情報
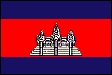

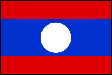
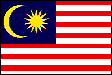
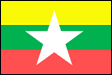
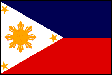
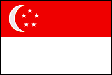
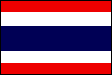
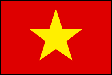

 Hungry Studioの「ブロックブラスト」、Sensor Tower APAC Awards 2025で「Best Puzzle Game」受賞
Hungry Studioの「ブロックブラスト」、Sensor Tower APAC Awards 2025で「Best Puzzle Game」受賞 ブラックハット・アジア2026、AIの脅威とサプライチェーンの脆弱性に関する画期的な調査を発表
ブラックハット・アジア2026、AIの脅威とサプライチェーンの脆弱性に関する画期的な調査を発表 タイ伝統 音楽・舞踊の夕べ
タイ伝統 音楽・舞踊の夕べ …and Action! Asia#04 -映画・映像専攻学生交流プログラム-公開上映・プレゼンテーション
…and Action! Asia#04 -映画・映像専攻学生交流プログラム-公開上映・プレゼンテーション FUN!FUN!ASIAN CINEMA 第1弾シンガポール映画『881 歌え!パパイヤ』上映
FUN!FUN!ASIAN CINEMA 第1弾シンガポール映画『881 歌え!パパイヤ』上映 映画で読み解くサンシャワー展!「ワーキングタイトル」国立新美術館で開催
映画で読み解くサンシャワー展!「ワーキングタイトル」国立新美術館で開催 東南アジアの短編ドキュメンタリー上映会Visual Documentary Project 2016
東南アジアの短編ドキュメンタリー上映会Visual Documentary Project 2016 淡路梅薫堂 江井工場
淡路梅薫堂 江井工場 インドネシア料理スラバヤ 調布店
インドネシア料理スラバヤ 調布店