あべ大臣の文部科学省は、共生社会の実現に向けて日本人などのマジョリティの変容が重要であるとして検討を進めているが、群馬県では日本人と外国人が対等な関係を構築して、母語や母文化を尊重する取り組みを実施していることが明らかになった。
文部科学省では、日本の公立学校に在籍している日本語指導が必要な児童生徒は大幅に増加し支援の充実が求められており、誰もが違いを乗り越え共に生きる共生社会の実現に向けたマジョリティの変容にもつなげていくことが重要であるとして、「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議」を開催していた。
今回は、第4回目となる会合が7月7日に開催された。議題は、『指導内容の深化・充実に関するこれまでの議論の整理』『外国人児童生徒等を包摂する教育、指導内容の深化・充実について(ヒアリング)』『その他』となる。
会合で配付された資料によると、群馬県教育委員会の教育長から『群馬県教育委員会の取組について』の説明が行われた。
この説明によると、わたしたちが目指すものは「みんなの違いで群馬に新しい価値を生み出そう」として、「日本人と外国人が対等な関係を構築」「誰一人取り残さず地域社会の一員として共生」「多様性を活かして多文化共生・共創社会づくりに貢献」であるとしている。
わたしたちの価値観は、「外国人児童生徒等を肯定的に受け入れる」「母語や母文化を尊重する」「多文化共生教育の推進」などであるとしている。
「母語・母文化の尊重」に関しては、「マイノリティの視点から多文化共生教育を考える」として、「母語対応のできる支援員の配置促進(補助事業)」「多様な子供がそのままの姿で肯定される環境づくり」などであるとしている。
「わたしたちの課題と対応」に関しては、「教諭以外の人的リソースの拡充」として、「母語やルーツにつながる支援員の生む安心感」「散在地域におけるキーパーソンの発掘」「多言語版の心理検査に対応可能な人材」などであるとしている。
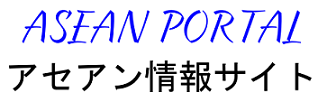

 アセアン10カ国情報
アセアン10カ国情報
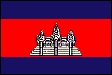

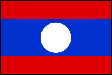
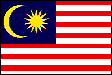
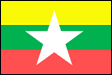
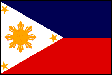
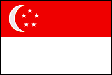
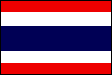
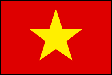

 高市政権はウクライナの医療体制強化と公正報道の確保等を支援、62億円無償資金協力
高市政権はウクライナの医療体制強化と公正報道の確保等を支援、62億円無償資金協力 福岡県はグローバル人材育成プログラム成果報告会、ベトナム現地で研修
福岡県はグローバル人材育成プログラム成果報告会、ベトナム現地で研修 高市政権はケニアの衛生改善を支援、USAIDからの支援減少UNICEFに6億円無償資金協力
高市政権はケニアの衛生改善を支援、USAIDからの支援減少UNICEFに6億円無償資金協力 フィリピン・アメリカと共同訓練、海上自衛隊のP-3C等が参加
フィリピン・アメリカと共同訓練、海上自衛隊のP-3C等が参加 アルゼンチン産牛肉の輸入解禁へ、鈴木農水相は国産への影響は現時点では不明と
アルゼンチン産牛肉の輸入解禁へ、鈴木農水相は国産への影響は現時点では不明と 茂木外相は避難民受入のエジプト支援で約5億円無償資金協力、大きな外交的意義があると
茂木外相は避難民受入のエジプト支援で約5億円無償資金協力、大きな外交的意義があると マレーシアで天皇誕生日祝賀レセプション開催、民生用原子力・AIの連携強化等
マレーシアで天皇誕生日祝賀レセプション開催、民生用原子力・AIの連携強化等 高市政権はマーシャル諸島の食料生産増加を支援、国際移住機関に2億円無償資金協力
高市政権はマーシャル諸島の食料生産増加を支援、国際移住機関に2億円無償資金協力 国際海事機関の事務局長がフィリピン訪問、日本郵船の研修所・商船大学を訪問
国際海事機関の事務局長がフィリピン訪問、日本郵船の研修所・商船大学を訪問 インドのヨギ首相は日本を日の出ずる国と、山梨県は実質的な交流を先導すると
インドのヨギ首相は日本を日の出ずる国と、山梨県は実質的な交流を先導すると Hungry Studioの「ブロックブラスト」、Sensor Tower APAC Awards 2025で「Best Puzzle Game」受賞
Hungry Studioの「ブロックブラスト」、Sensor Tower APAC Awards 2025で「Best Puzzle Game」受賞 ブラックハット・アジア2026、AIの脅威とサプライチェーンの脆弱性に関する画期的な調査を発表
ブラックハット・アジア2026、AIの脅威とサプライチェーンの脆弱性に関する画期的な調査を発表 タイ伝統 音楽・舞踊の夕べ
タイ伝統 音楽・舞踊の夕べ …and Action! Asia#04 -映画・映像専攻学生交流プログラム-公開上映・プレゼンテーション
…and Action! Asia#04 -映画・映像専攻学生交流プログラム-公開上映・プレゼンテーション FUN!FUN!ASIAN CINEMA 第1弾シンガポール映画『881 歌え!パパイヤ』上映
FUN!FUN!ASIAN CINEMA 第1弾シンガポール映画『881 歌え!パパイヤ』上映 映画で読み解くサンシャワー展!「ワーキングタイトル」国立新美術館で開催
映画で読み解くサンシャワー展!「ワーキングタイトル」国立新美術館で開催 東南アジアの短編ドキュメンタリー上映会Visual Documentary Project 2016
東南アジアの短編ドキュメンタリー上映会Visual Documentary Project 2016 淡路梅薫堂 江井工場
淡路梅薫堂 江井工場 インドネシア料理スラバヤ 調布店
インドネシア料理スラバヤ 調布店