このページの所要時間: 約 1分7秒
日本の都道府県における国際交流の相手は、中国が最も多く、行政や教育の分野で交流していることが明らかになった。
一般財団法人の自治体国際化協会では、地方自治体などが国際交流事業を実施する上で参考としてもらうため、毎年度自治体の国際交流事業の実績を調査し、その結果を公表している。
今回は、令和7年度の調査結果を発表した。調査時期は、令和7年5月から6月となる。調査対象は、令和6年度に国際交流事業を実施した地方自治体となる。
調査した結果、令和6年度中に実施された国際交流事業の総数は、3,202件(都道府県672、市区町村2,530)であり、国内696の自治体(都道府県40、市区町村656)と、海外248の国・地域との間で実施されていた。
都道府県における、相手国・地域別の交流事業内容の件数は、中国128、韓国82、アメリカ合衆国60、台湾59、ベトナム58、オーストラリア29、タイ25、フランス19、ドイツ18、ブラジル18となる。中国との交流の内訳の件数は、行政45、教育33、経済27、文化9、スポーツ6、保健、医療、福祉2、ホストタウン1となる。
国際交流活動にかかる1自治体あたりの総事業費では、都道府県では、5,000万円以上が16団体となり、割合では40.0%と最も多くなっていた。
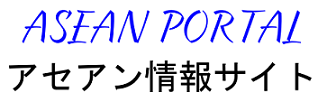

 アセアン10カ国情報
アセアン10カ国情報
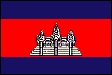

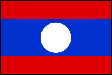
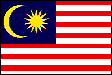
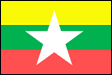
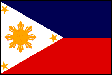
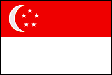
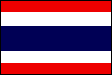
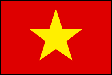

 高市政権はウクライナの医療体制強化と公正報道の確保等を支援、62億円無償資金協力
高市政権はウクライナの医療体制強化と公正報道の確保等を支援、62億円無償資金協力 福岡県はグローバル人材育成プログラム成果報告会、ベトナム現地で研修
福岡県はグローバル人材育成プログラム成果報告会、ベトナム現地で研修 高市政権はケニアの衛生改善を支援、USAIDからの支援減少UNICEFに6億円無償資金協力
高市政権はケニアの衛生改善を支援、USAIDからの支援減少UNICEFに6億円無償資金協力 フィリピン・アメリカと共同訓練、海上自衛隊のP-3C等が参加
フィリピン・アメリカと共同訓練、海上自衛隊のP-3C等が参加 アルゼンチン産牛肉の輸入解禁へ、鈴木農水相は国産への影響は現時点では不明と
アルゼンチン産牛肉の輸入解禁へ、鈴木農水相は国産への影響は現時点では不明と 茂木外相は避難民受入のエジプト支援で約5億円無償資金協力、大きな外交的意義があると
茂木外相は避難民受入のエジプト支援で約5億円無償資金協力、大きな外交的意義があると マレーシアで天皇誕生日祝賀レセプション開催、民生用原子力・AIの連携強化等
マレーシアで天皇誕生日祝賀レセプション開催、民生用原子力・AIの連携強化等 高市政権はマーシャル諸島の食料生産増加を支援、国際移住機関に2億円無償資金協力
高市政権はマーシャル諸島の食料生産増加を支援、国際移住機関に2億円無償資金協力 国際海事機関の事務局長がフィリピン訪問、日本郵船の研修所・商船大学を訪問
国際海事機関の事務局長がフィリピン訪問、日本郵船の研修所・商船大学を訪問 インドのヨギ首相は日本を日の出ずる国と、山梨県は実質的な交流を先導すると
インドのヨギ首相は日本を日の出ずる国と、山梨県は実質的な交流を先導すると Hungry Studioの「ブロックブラスト」、Sensor Tower APAC Awards 2025で「Best Puzzle Game」受賞
Hungry Studioの「ブロックブラスト」、Sensor Tower APAC Awards 2025で「Best Puzzle Game」受賞 ブラックハット・アジア2026、AIの脅威とサプライチェーンの脆弱性に関する画期的な調査を発表
ブラックハット・アジア2026、AIの脅威とサプライチェーンの脆弱性に関する画期的な調査を発表 タイ伝統 音楽・舞踊の夕べ
タイ伝統 音楽・舞踊の夕べ …and Action! Asia#04 -映画・映像専攻学生交流プログラム-公開上映・プレゼンテーション
…and Action! Asia#04 -映画・映像専攻学生交流プログラム-公開上映・プレゼンテーション FUN!FUN!ASIAN CINEMA 第1弾シンガポール映画『881 歌え!パパイヤ』上映
FUN!FUN!ASIAN CINEMA 第1弾シンガポール映画『881 歌え!パパイヤ』上映 映画で読み解くサンシャワー展!「ワーキングタイトル」国立新美術館で開催
映画で読み解くサンシャワー展!「ワーキングタイトル」国立新美術館で開催 東南アジアの短編ドキュメンタリー上映会Visual Documentary Project 2016
東南アジアの短編ドキュメンタリー上映会Visual Documentary Project 2016 淡路梅薫堂 江井工場
淡路梅薫堂 江井工場 インドネシア料理スラバヤ 調布店
インドネシア料理スラバヤ 調布店